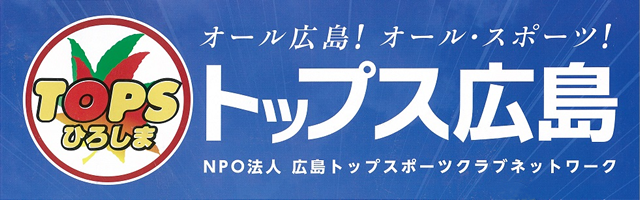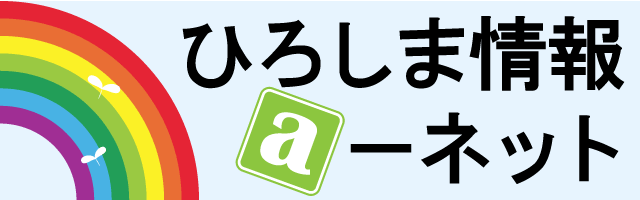詳しい案内(ソメイヨシノ誕生の背景)
日本に自生する原種のサクラは11種(オオシマザクラ、ヤマザクラ、エドヒガンなど)あり、自然の交雑でその変種も多く、古くから庭などに植えて愛好されてきました。
太平の世が続いた江戸時代中期は、武士から庶民まで巻き込んだ一大園芸ブームが巻き起こりました。江戸の染井村に植木職人が集まり、サツキを始めとする庭木の栽培品種の改良と生産が行われようになりました。
サクラについても川土手などにサクラ並木が作られ、サクラの植栽が盛んになると、各地のサクラが染井村に集められ、苗木の生産が行われるようになりました。
オオシマザクラは、ヤマザクラから分れ伊豆諸島の島の生育環境に適合する進化をとげ、「成長が早く形質の変異が起こりやすい性質」をもっています。
染井村の職人により、このオオシマザクラの花粉をエドヒガンの雌しべに受粉させて産み出されたのがソメイヨシノの原木で、「吉野桜」という名前で苗木が生産されました。(※ソメイヨシノの由来には諸説があります。)
明治初期に上野山の桜の調査が行われ、植えられたサクラの中で他に際立った性質のサクラがあることが知られ、染井村で生産されたサクラであることか確認されました。
その後、栽培品種の名前を「ソメイヨシノ」とし、明治中期から日本全国の城跡や堤防、公園などに盛んに植栽され、多くの桜の名所が産まれました。
( コラムについて )
サクラやソメイヨシノの由来につては、現在も研究が進められており、まだ定説が定まっていません。そのなかで有力と思われる2つの説
①「サクラが何処で産まれ、どのような道筋をたどり日本にやって来たのか」
②「2筋の道で日本にやって来たサクラが、また一つになるなかでソメイヨシノが誕生する物語」
について2編のコラムで紹介しています。

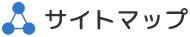
 広島市スポーツ協会トップへ
広島市スポーツ協会トップへ